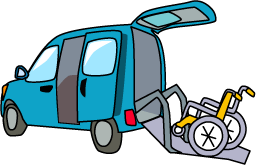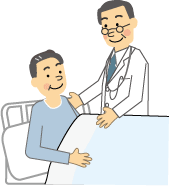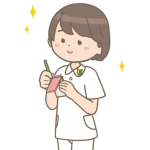「犬たちはとてもかわいかったよ」
笑顔で話されます
その同じ日
受け持ちの看護師さんに思い切って相談をされました
「以前からずっとお世話になっていた先生に会いに行きたい
今までのお礼を言いたい」
この一言を
スタッフみんなと共有しました
――ぜひ望みを叶えたいね!
すでにベッド上で寝たきりに近くなっていたCさん
さらに医療用麻薬の持続皮下注射の器械もつながっています
ご家族と話し合いを持った結果
残された時間は多くないので
翌日に出かけましょう
ということになりました
リクライニングの車いすの手配
介護タクシーの予約
薬剤の準備
などなど急いで行いました
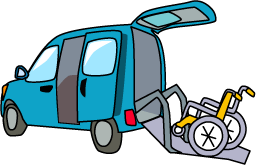
ご家族には
道中もし病状の悪化があれば
すぐに病院にもどってくることを告げ
さらに私と受け持ちの看護師さんも同乗すること
の合意をいただきました
このときの看護師さんたちの動きはとても素早いものでした
スタッフひとりを付き添いに送り出すことについて
みんながすぐに集まって意思統一しました
私はとても感謝しています
――準備が整った日の夜のことです
Cさんはこの外出が最後となることを
十分に悟っていました
優しいお母さんの前で
涙を流されたとお聞きしました
また
「ふたりで○○を酌み交わしたいですね」
と診察のときに私が何気なく言った言葉を
覚えておられました
約束は果たさなければなりません
勤務時間を終えてさっそく
病室へ
一口ずつ…
ほんのりとした気分で
話をしました

私はCさんに語りかけました
「今まで思いをため込んでいるのではと心配していました
でも今回お気持ちをいっぱい聞かせていただけてよかったです」
「さいごまでいっしょにがんばります」
Cさんの涙をみて
私も…
けっして○○のためではないと思います
いよいよ外出のときです

Cさんはすべてを私たちにまかしたという表情をされています
外は快晴
少し汗ばむ陽気です
介護タクシーのなかはクーラーがきいて快適
道中
Cさんはご家族や私たちからの話に静かにうなづいていました
緊張が伝わってきます
15分くらいで目的の診療所に到着

患者さんたちがたくさん診察を待っていました
ご家族からすでに連絡をされていたので
診察室に車いすごと通していただきました
さあ
長年お世話になってきた先生と
ご対面です
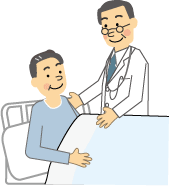
顔をみるなり
Cさんから大粒の涙が…
私はCさんのそばにいたので
医師の言葉がはっきりと聞こえました
――私の医師人生は
Cさんとともにあったのです
胸をうつ一言でした
(私も同じ言葉を患者さんに伝えることができるのだろうか?)
これまでの経過を報告して
診療所をあとにしました
それから数日後
Cさんはご家族みなさんに見守られながら
静かに旅立たれました
その間には
まったく食事がのどを通らなかったけれど
お好み焼きを食べたいと希望され
少しであるけれど
食べることができました
とご家族が喜ばれている姿も
見ることかできました
「入院患者さん」とひとくくりにはできません
人は様々です
お付き合いの仕方も当然異なってきます
緩和ケア病棟での
短いお付き合いのなかで
日常のなにげない会話のなかに
スピリチュアルな課題が見えてくることがあります
「寿命は短いのだからべつにしておきたいことなんてないです」
「だんだんと動けなくなってきて、今さら何ができるんでしょうか」
「外出がしたいなあ、でも家族に負担をかけてしまうのであきらめます」
など
元気な人からみれば
小さな望みなのかもしれません
何度もくり返しますが
日常のなにげない会話のなかで
不安や苦悩が
見えてくるのです
私の反省でもあります
どうしても薬に頼ってしまいます
スピリチュアルペインといわれている
患者さんの苦悩に
私たちの時間を
少しでも
使うことができるなら
(ある人は「時間を注射する」と言われていました)
これから
もっと考えていかないといけないテーマです