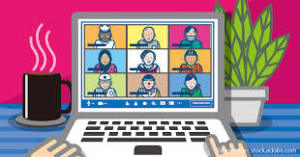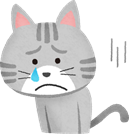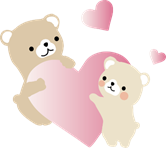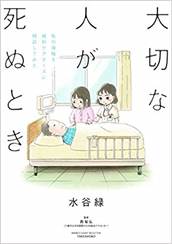私たちの法人の機関誌「三つの輪」に
毎回いたやどクリニックの木村院長(小児科医)が
コラムを載せています
“カンガルーのポケット”
というコラムです

今回は新型コロナウイルスがテーマです
しかし発行されるのが4月になるので
木村院長の了解をいただき
緩和ケア病棟のブログに
先行して載せさせていただきました
ぜひ眼を通していただきたい文章です
カンガルーのポケット
こころへの感染を防ごう
小児科医 木村彰宏
「今日は△人に、新たな感染が確認されました」。テレビをつけると、新型コロナウィルスのニュースが飛び込んできます。2019年11月に中国で確認された原因不明の肺炎は、世界中に不安を拡げています。
コロナウィルスは、1万分の1㎜の小さな球形RNAウィルスで、風邪の原因の10~15%を占めるといわれます。自力で生きることができないために、ヒトやイヌ・ネコ・スズメなどお気に入りの動物を居場所として生活しています。ウィルスの立場から考えると、居場所を提供してくれる動物に過度のダメージを与えて殺してしまうのは愚かな選択です。風邪ひき程度に軽く感染させた動物が次の動物に出合い、自分を拡げてくれるとラッキーです。コロナウィルスは種の壁を超えて他の動物に感染することは稀とされていますが、はじめて出会う動物に感染し暴走することがあります。2002年のSARS、2012年のMERS、そして今回のCOVID-19がそれにあたります。
◇流行の終息はいつなの
2009年に大流行した新型インフルエンザは、今では季節性のインフルエンザとして定着しています。ウィルスからすればヒトと共存可能なタイプに変異する方がお得でしょうし、ヒトからすれば適度な免疫力を獲得し、風邪のひとつとして対応できるようになるでしょう。共存可能な関係ができるまで、迅速検査法や治療薬の研究、ワクチンの開発が急がれます。
◇こころへの感染を防ごう
<ご高齢の方へのお願い>
- 手洗い、うがい、マスクは感染対策の基本です。
- 人がたくさん集まる狭い場所に出かけるのは避けましょう。
- 身体を動かすなら公園でのラジオ体操や、人通りが少ない通りでのお散歩がお勧めです。
- 基礎疾患の治療を続けましょう。病院に通うことが難しければ電話を使って診察を受けて、お近くの薬局に処方せんをFAXしてもらえる方法もあります。
- 親しい方と連絡を取り合いましょう。電話やスマホを使って、声を聞くだけでも元気がでますよ。
感染を避けられないのなら、できる限りあとでかかるようにしましょう。時間が経てば、世界中の研究者からより適切な治療法が提案されるはずです。
<子どもたちへのお願い>
- 早寝、早起き、しっかり食べて、生活のリズムを大切にしようね。
- お天気の日は、公園で身体を動かして遊ぼう。
- ゲームをするならテーブルゲームがお勧めです。オセロやトランプ、将棋や人生ゲームなど、おうちの人や友だちと一緒に楽しめるゲームがたくさんあるよ。何かひとつ名人になって、みんなを驚かそうね。
- テレビゲームは時間を決めて。これがなかなか難しいんだなあ。おうちの人と一緒にできるソフトなら時間を守れるかも。
- スマホを見るなら、科学番組がお勧め。学校で習わなかったことを勉強して博士になろう。
- 今まで手にしなかった種類の本を読んでみよう。マンガで描かれた歴史の本や、鉄道やお城、宝石の図鑑、手芸の雑誌など、おとなになってからの楽しみにつながるかもよ。
- 一日一回は大笑いをしよう。流行のお笑い番組だけでなく、落語にも挑戦してみよう。
- 子どもシェフをめざそう。おにぎりや玉子焼き、野菜炒めからはじめて、おとうさんやおかあさんを驚かそうね。
君たちが笑顔をみせて元気で過していると、おとなも元気でがんばれます。
一生の間に一度経験するかしないかの大変な毎日が続きますが、こころの中まで感染しないように乗りきりましょう。
カンガルーも、マスクをはずして笑いあえる日が来ることを、楽しみに待っています。